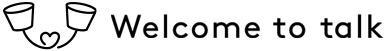BLOG
こころの専門家リレーメッセージ
家族療法-子どもを置いてきぼりにしない
臨床心理士・公認心理師
竹澤 綾
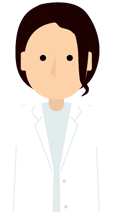

学生時代の研究は一貫して「家族療法」。大学時代のテーマは「怒り」、大学院では「家族」をテーマに論文をまとめました。
家族療法では、悩みや症状を抱えている子どもの問題ではなく、家族全体をひとつのシステムとしてとらえ、家族全体の問題として考えます。何かしら起こっている事象は、おじいちゃんやおばあちゃん、お父さん、お母さん、兄弟姉妹から伝播され、影響を与え合います。虐待は、伝播されるものの代表例です。ぐるぐると循環しているため、問題そのものだけではなく、多方向からアプローチできるという柔軟さがあり、悪循環をどこかで止められるよう、家族全体の関係づくりを大切にしています。
大学院生の頃から4年間、東京都ひきこもりサポートネットで児童・思春期のひきこもりやその家族のサポートを行っていました。現在は、子ども家庭支援センターや保育所、小児科クリニック等で、主に未就学児の発達支援や子育て相談の仕事を行っています。具体的には、子どもの発達のアセスメントや子どもを対象としたカウンセリング、保護者の心理支援、保育所等の職員と対象の園児について理解を深める話し合いです。
いろんな考えを一旦置いて、子どもに関わる方たちと一緒に考える関係づくり。未就学児対象のいろんな人が関わる場面で、家族療法の学びが活かされています。
常に感じるのは、子どもに関わるほとんどの人は子どものためを思って行動しているということ。そうした大人の“熱い”思いが価値観の押し付け合いにならないよう、心理士として、当事者の子どもたちが安心して成長できる環境を整えることに注力しています。
また子どもの年齢によって関係者が気にかけるタイミングやポイントにズレがあるように思います。小学校に上がる前は、園の先生方は「将来が心配」とご相談がある一方で、保護者の方は「楽しく過ごしているから大丈夫」と気にしません。小学校に入学すると、先生たちは「言うことを聞かない生徒がいて困っている」、保護者の方は「いつも子どもが先生に怒られているのが嫌だ」と言います。
集団の中で子どもたちと対峙する先生と、家庭の中で1対1で接する保護者。こうした集団と個の関係性の違いからさまざまなギャップが生じています。第3者の専門家として、それぞれの思いを共有したうえで介入すると、先生と保護者の関係性が良くなることがあります。互いが高め合えるような言葉を通じた心理支援をこころがけています。
「相談したことで新しい1歩を踏み出し、良い方向に進んでいる」というお話を聞けると大変嬉しく思います。
『マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ』
小説/2015年11月発売/著者:古内 一絵/出版社:中央公論新社https://www.chuko.co.jp/special/makanmalam/
どんな人も悩みながら生きている。元エリートサラリーマン、今はドラッグクイーンの店主が、食べる人を思って作った美味しい料理がお腹を満たすと共に、苦しくて渇いたこころを、温かい言葉が満たしていく。読んでいるこちらまで、緊張しているこころも緩むような優しい物語です。
<この記事を書いた人>
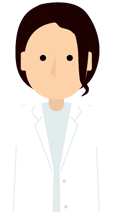
発達臨床心理学
キャンプでは自然に囲まれてゆっくり過ごすと頭がスッキリします。黙々と集中できる編み物は、適度な疲れも心地よい。麻ひもで作ったかごバックは重宝しています。