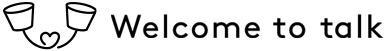BLOG
こころの専門家リレーメッセージ
分け隔てなく、フラットであること
精神科医
山森 佐智子

部活動一色の学生時代。中学から始めたバレーボールに情熱を捧げていました。ポジションは、アタッカーにトスをあげるセッター。調子の良し悪しや性格を考慮して、どのアタッカーにトスを上げるかを判断していました。振り返ってみると、人をみる楽しさに気づく原体験になったようにも思います。
ちょうど学生時代にレシーブ専門の「リベロ」のポジションが導入され、背の低いプレイヤーにも活躍の機会が増えました。バレーボールだけではなくチームスポーツ全般にいえますが、ブロック、スパイク、トスなどそれぞれの役割分担があり、それぞれが仕事をすることでひとつのチームが完成する点が魅力でした。
高校卒業後は、精神科医であった父親の影響から医学部に進学。田舎の町医者であった父は、「からだのことも、こころのことも、調子が悪ければ来てください」というスタンスで診療にあたっていました。実家の真向かいに父の病院があったことから、私も風邪をひいたりすると父に診てもらうこともしばしば。小さい頃から、父の診療=医師が身近な存在であり、医師になる道を選んだのは私にとって自然な流れでした。
そして、迷わず精神科医を選んだのは、大学時代にその父が亡くなったことが大きかったかもしれません。その後の学生実習で一番やりがいを感じたのも精神科でした。「じっくりと話をする」「患者さんとの関係性をつくる」ことが大事な点に惹かれました。とはいえ、へそ曲がりな私は、父がもし生きていたら「同じ精神科であれこれ言われるのもなぁ」と別の科を選んでいたようにも思います。
こうして父と同じ精神科医を志すようになりました。
医師としての父のこだわりは、白衣の下は必ず長袖のワイシャツを着ること。服装はパリッとしなくてはという思いが強かったのでしょう。患者さんが大人でも子どもでも、分け隔てなく優しい口調で対応していた姿勢を見習っています。
精神科は最も人とのかかわりを大事にする科であることが魅力的な反面、時に難しく大変なこともあります。それでもやはり、患者さん一人ひとりのバックグラウンドが重要になってくるため、個々の事情を踏まえて診療にあたる点にやりがいを感じています。
先入観を持たずに、決めつけず、個々に対応する。「いつもフラットでいること」を意識しています。
「出会う人はすべて、嫌な人かもしれないと思え」
高校最後の卒業式の日に、担任の先生からの言葉です。普段のホームルームでは連絡事項以外の話は一切しない先生でした。「なんてこと言い出すの!?」と驚いたのですが、この言葉には続きがあり「その方が、いい出会いに感謝できるから」と。こころに残る言葉であり、今も一つひとつの出会いに感謝する日々を送っています。<この記事を書いた人>

中学・高校・大学はバレーボール部に所属。夏の海で部活の仲間とビーチバレーをしたこともいい思い出です。社会人になってから習い始めたヨガは、呼吸やリラックスなど、日常から少し離れた感覚を味わえます。